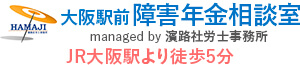双極性障害(躁うつ病)で障害年金を請求するには
双極性障害は、「躁状態」と呼ばれる気分が高ぶったとき、「うつ状態」と呼ばれる気分が低下したときが、交代して起こる病気です。「双極性障害Ⅰ型」と「双極性障害Ⅱ型」の大きく2種類に分けられ、躁病を経験したことがある場合は「双極性障害Ⅰ型」と診断され、うつ病に加えて軽躁病を経験したことがある場合には「双極性障害Ⅱ型」と診断されます。発症する年齢は、30 歳くらいが平均的ですが、中学生から高齢者まで、さまざまな年齢で発症します。遺伝や環境、ストレスなどが原因となり、脳内の神経伝達の異常によって引き起こされると言われています。
双極性障害もうつ病と同じく、体調の良い時と悪い時を繰り返すため、認定において、現症のみによって判断するのではなく、「症状の経過及び日常生活活動の状態を考慮する」とされています。
うつ状態では通院もままならず、躁状態の時しか通院していないという場合は、医師が躁状態しか見ていない為、うつ状態の時のことやや家での状況を、エピソードを交えて医師に伝えておく必要があります。
躁うつ病(双極性障害)による障害年金の認定基準
(1)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである
| 障害の程度 | 障害の状態 |
|---|---|
| 1級 | 高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりする為、常時の援助が必要なもの |
| 2級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
| 3級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
(2) 気分(感情)障害の認定に 当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(3)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
躁うつ病(双極性障害)の受給事例はこちら
無料相談のご予約を受け付けしています。06-6131-5918相談受付 9:00-21:00 [年中無休](担当:濱路)
24時間受付のメールでのご相談はこちら お気軽にお問い合わせください。