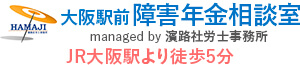大阪府で障害年金に強い社労士という事務所はたくさんありますが、どのようにして社労士を選べばよいですか?

以前と比べると、障害年金を業務として取り扱う社労士事務所は大阪府下でもかなり増えてきております。
選択するにあたってのポイントとしては、大きく分けると下記の7つに分けられると思います。
1.自宅から行ける距離にあるか。
社労事務所に障害年金の申請代行を依頼すると初回の相談や契約、ヒアリング等で少なくとも1~2回は事務所に出向く必要があります。その為、ご自宅から行ける場所に事務所があるかということは、重要になってくるかと思います。
出張相談に対応している事務所の場合は、自宅近くまで来てもらうことも可能かと思いますが、この場合も自宅が出張対応エリアに入っているかの確認は必要になってくるかと思います。
一方でコロナ禍以降、ZOOMやLINE通話などのWEBによる面談方式も定着してきた感がありますが(当事務所でも月に数人の方からご要望があります)、「一度直接会って話をしてみないと契約は不安だ」という方もまだまだいらっしゃいますので、この辺りは個人の価値観次第になってくるかと思います。
2.ご自身の傷病の実績はありそうか。
障害年金の対象となる傷病は多岐にわたっており、難病等の症例が少ない傷病に関しては取り扱ったことが無いという社労士事務所は当然あるかと思います。
多くの社労士のホームページでは「受給事例」等のページがあると思いますので、ここである程度各傷病の実績はわかるかと思います。
障害年金の傷病ごとの全体の割合としては、精神障害や知的障害で約6割、肢体の障害で約2割、糖尿病や腎疾患等の内科的疾患で1割弱となっており、その他の傷病で残りを占めます。
精神疾患は障害年金の大部分を占めている事から、精神疾患を扱ったことが無いという社労士はいないと思われます。
3.実績件数はどれくらいありそうか。
上記2と関連してくるところではありますが、やはり実績は多いに越したことはないと思います。
当たり前ですが、多ければそれだけ数多くの事例を経験していますので、
「初診のカルテが無い場合での他の書類での初診日認定の可否判断」
「就労中の等級認定の可否判断(がん・精神疾患等)」
「社会的治癒等の難案件の対応」
等の認定されるか微妙なケースでは、実績が少ない事務所と比較すると差が出てくると思います。
故に1つ目の相談先の事務所で「受給は無理です」と断られたとしても、他の事務所もあたってみるべきであると思います。
4.通院先の病院について詳しそうか。
障害年金申請において最も重要と言っても過言ではない書類に「医師の診断書」があります。当然通院先の主治医に書いてもらう必要があります。
診断書を依頼する際に病院指定の依頼フォーマットがある場合や、指定の受付窓口や担当がいらっしゃる場合もあり、病院によって進め方が異なります。。
また、医師によっては障害年金を含む社会保険制度について消極的な考えを持っておられる方もいらっしゃいます。(勿論、その逆の考えの方も大勢いらっしゃいます。)
そもそも、「診断書等の書類は書かない」という方もいらっしゃいます。
さらに、診断書の内容にも医師によって傾向がありますので、診断書の依頼の仕方やタイミングについての留意事項は多いです。
この辺りは当該病院に過去に複数回診断書を依頼したことが有ればデータとして残している事務所が多いと思いますので、対応地域が広い事務所よりも、地域密着の事務所の方が当該地域の病院のデータ量は多いと思われます。
5.審査請求にもつれ込んだ場合は対応可能か
障害年金は初回の請求(裁定請求)が不支給(又は決定された等級が不服がある)であった場合は「審査請求」を行うことができます。不支給があったことを知った日から3か月以内に、管轄の社会保険審査官に対して審査請求の理由等を添えて提出します。
その後、追加での質問書の提出や保険者(不支給の決定を下した日本年金機構)の意見書が交付された後に、各厚生局(近畿エリアの場合は「近畿厚生局:大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1−22」)で、保険者との口頭意見陳述があります。
事前に提出した質問書に対する回答や、その他の質問事項について保険者の意見の確認を行い、保険者が下した決定が間違っていることを主張します。ここでは社会保険審査官も同席します。
審査請求でも結果が覆らない場合は再審査請求→訴訟と移行します。
これらの審査請求以降の手続きは、初回の請求(裁定請求)とは社労士が作成・収集する書類の難易度は格段に上がります。
また、口頭意見陳述もありますので、「コミュニケーション能力」や「等級基準や各ガイドラインに基づいた理論的な主張」を行えるかも必要とされます。
この審査請求ですが、障害年金業務を行っている社労士の全てが携わっていないのが現状です。
残念ながら、日本年金機構の下す決定にはしばしば誤っていると思われるものがありますので(その証拠に、審査請求に対しての日本年金機構自らの「初回の処分変更」や、社会保険審査官の「初回の処分の取り消し」の決定は頻繁にあり、当事務所で審査請求を行ったものでは5割前後は決定が覆ります。
おそらく社労士に相談せずに不当な決定を甘んじて受け入れている、若しくは不当であると気付かないケースは多いと想定されます)、審査請求のノウハウは必須であると考えます。
6.担当する社労士とは相性は合いそうか。
障害年金は申請を開始してから請求完了まで2~3か月、そこから審査で3か月、審査後の入金まで1~2ヶ月を要しますので、合計で半年以上かかります。
審査請求以降にもつれ込むと年単位になります。
この間、担当の社労士(場合によっては事務員)と電話やメール、直接会っての面談等でのコミュニケーションを行う必要がありますので、相性が合わないとコミュニケーションが苦痛になると想定されます。
物腰が柔らかそうか、質問には答えてもらえそうか、その他性別や年齢層、顔写真がある場合は見かけ等も判断の要素になってくると思われます。
知人や医療機関からの紹介であれば事前の情報がありますが、無い場合は実際会ってみるか、グーグルの口コミ等での判断になってくると思われます。
7.費用はどの程度になるか
障害年金の請求代行の社労士費用は大きく3つに分けられます。
着手金:0円~3万円程度
受給した場合の報酬:2か月分~3か月分程度
遡及して受給した場合の報酬:遡及した分の5%~20%
着手金が無料であっても診断書や証明書、住民票等の書類代金や、申請にかかる交通費や郵送費の実費分が別でかかる場合はあると思います。
また着手金は無料ですが、代わりに事務手数料という名目で数万円を着手時に支払うケースも有るようです。
費用の許容範囲は、個人の経済的事情で変わってくると思いますので、ホームページ上の費用のページの比較や、実際の説明を聞いてからの判断になるかと思います。
番外編
障害年金の申請における「受給率」という数字はそこまで気にする必要はないかもしれません。
例えば、そこまで複雑ではない案件を年に5件代理申請して、それが全て通れば「受給率100%」となりますし、他事務所が断った受給が難しい難案件を年間5件代理申請して、4件通ったしても「受給率80%」です。
私の観測範囲ですと、経験と知識が豊富で、審査請求も積極的に手掛ける熟練の社労士は後者が多い印象です。
以上、大きく7つに分けて社労士事務所の選び方についてご説明させていただきました。皆様の社労士選びの一助になれば幸いです。
(本回答は、2022年4月時点でのものです。)
障害年金の申請手続きは慎重にお進めください。

社会保険労務士 濱路陽平
障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。
しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。
当事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。
請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。
1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる
2.初めて病院に通った日から1年6月経過している
3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)
4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。
1~4に当てはまる方のご相談のご予約は
06-6131-5918まで
または下記からお問い合わせください。